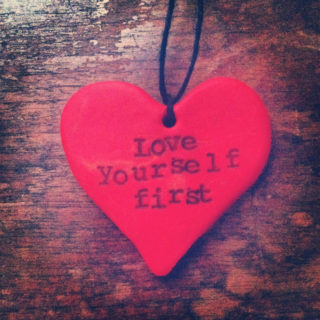呼吸がすべて
こんにちは!ゲスト・ティーチャーの川原朋子です。
先週、東京で11月に雪が降るのは54年ぶりという日に、無事バリから日本に戻りました。その気温差はおよそ30℃。わたしにとっては、秋を飛び越え、いきなり冬に突入してしまったようなもの。冬の服装はしていても、まだどこか「今ここ」に馴染みきれていないような感覚があります。
環境や、気温の変化といった大きなものだけでなく、人は気づかないような小さなことにも、ストレスを感じてしまう生きものです。どんなことであれ、自分の心や身体の健やかさを脅かすようなものを「敵=ストレス」と判断し、自らを守ろうとする機能をわたしたちは持っています。それが「闘争逃避反応」と呼ばれるもの。文字通り、敵に闘いを挑んでやっつけるか、その敵から逃げて、安全な状態を取り戻そうとする自己防衛本能のことです。そのモードに入っているとき、わたしたちの自律神経は、交感神経が刺激され、呼吸は早く浅くなり、いつでも闘える、あるいは逃げることができるように、血液が主に腕や脚に流れるようになります。
それが、一過性であれば問題ありませんが、慢性的なストレスにさらされ、常時交感神経が優位になっていると、呼吸や血液が十分に巡らないことの弊害が出て、心や身体の不調を招くことになりかねません。あらゆる病気の原因の9割はストレスであると言われる根拠は、そこにあるのです。
もといた場所に戻ってきたとは言え、わたしも目下、帰国後のストレスの影響を多分に受けています。プライベートでの大きな変化もあり、それは幸せな展開でもあるのですが、色々な可能性がある分、先が見えない不安も抱えています。交感神経が働いているとき、わたしたちは左脳が優先になり、何とか答えを出そうと考えをめぐらせてしまうものです。向き合っている問題が大きく、そう簡単に答えが出ないときは、残念ながらそれがまた、新たなストレスを生む原因になってしまいます。
論理的に物事を考えることは、生きて行く上でもちろん大切ですが、あまりに頭を悩ませ、それが自分の心身に負荷をかけてしまうのはよくありません。「考えないようにしよう」「もう考えないようにしよう」と思っても、そう簡単に頭を切り替えられる人ばかりでもないでしょう。わたしもどちらかというとそういうタイプで、まさにこの数日間がそうだったのですが、悩むことに疲れてしまい、少しでも考えないでいられる状況に自分を入れてあげようと思い直しました。
それはただ、呼吸を深めること。まずは思い切りため息をつくだけでもいいのです。呼吸と神経系は密接につながっていて、呼吸がゆったり深くなると、わたしたちに弛緩(リラクゼーション)反応をもたらしてくれる副交感神経が、自ずと優位になります。副交感神経が働いているときは、右脳が優先になり、脳は考えるというモードから「感じる」モードに切り替わります。大きなため息をつくと、一瞬でも心が軽くなるというのは、気のせいではありません。それは、色々なことを考えすぎて凝り固まった頭を、お休みさせてあげることにもなるのです。
わたしたちの身体がもともと持っているこのメカニズムを利用し、心身共に深いリラックスを堪能するのがリストラティブ・ヨガ。そして、ポーズをするために呼吸をするのではなく、呼吸をするためにポーズをとるのがハート・オブ・ヨガ。リストラティブ・ヨガは『究極のリラクゼーション』、ハート・オブ・ヨガは『動くプラーナヤマ(呼吸法)』とも呼ばれています。
リストラティブ・ヨガは、今日(11/30)から12/21まで、毎週水曜日19:15〜20:45。ハート・オブ・ヨガは、12/3から12/17まで、毎週土曜日16:45-18:15にクラスがあります。ヨガがまったく初めての方でも問題ありません。お時間とお気持ちの合う方は、是非お越しください。呼吸をすることの心地良さと大切さを、ご一緒に味わえることを楽しみにお待ちしています。
Love,
tOMoko ♡
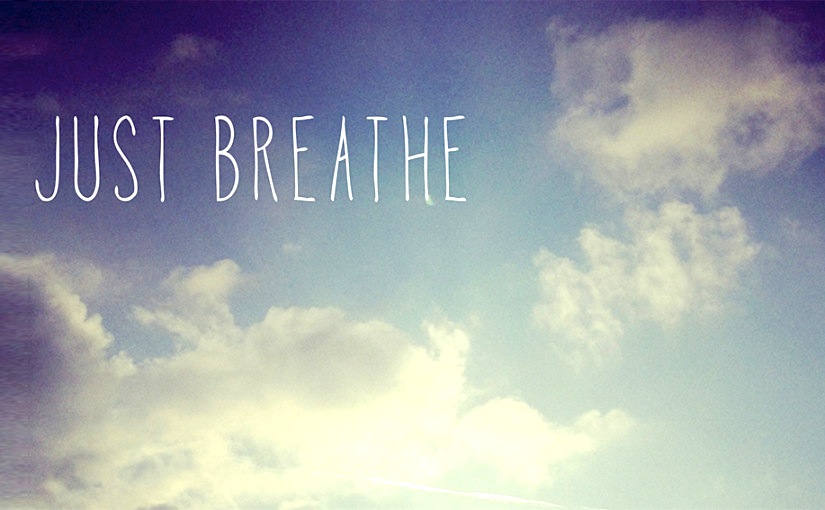
【ヨガコラム #5】委ねること
なかなか考えても答えが出ない大きなものから、ほとんど意識しないような小さなものまで、人生は日々決断の連続です。何かを選ぶことで、何かを失うこともあります。呼吸に例えるならば、息を吸い続けることができないように、すべてを留めておくことは無理だからです。何かを得るためには、何かを手放さなくてはなりません。生きるということは、その取捨選択の上に成り立っています。
手放すことで舞い込む苦労と、手放さないことで背負う苦労があるなら、勇気を持って前者を選びたい。今は、そんな心境です。現状に留まるか、一歩踏み出すか。その二つの間で揺れ動き、あれこれ思考が巡ります。失敗したくないと、先回りして考え過ぎると、それが自分の自由を奪ってしまいます。一方で向こう見ずに飛び出して、路頭に迷ってしまうこともあるかもしれません。
考えても考えても、結論が出ず、時間ばかりが過ぎていく。中途半端な状態が長く続くと、それがストレスになってしまいます。地に足が着かず、宙ぶらりんでいる感覚は、あまり心地の良いものではありません。それに耐えかね、いずれ決断のタイミングが来るのだと思います。考えるだけ考えたら、どちらであっても自分の選択を信じ、委ねるしかありません。いい意味で「なるようになる」と開き直ること。だからと言って、何も努力をしない訳ではありませんが、その結果に執着をしないようにするということです。
それを、ヨガでは「ヴァイラーギャ(離欲、無執着)」と呼びます。口で言うほど簡単ではありませんが、今のわたしにとって一番必要なものです。
新しい世界、未知なるものには、不安がつきものです。自分の安全地帯を飛び出そうとしているならなおのこと。でもそこにこそ、無限の可能性が待っています。それを受け取ることを許せるのは、自分だけです。
“Enlightenment is when a wave realizes it’s the ocean.”
—Thich Nhat Hanh
「悟りとは、波が自分は海だと気づくこと」
(ティック・ナット・ハーン)
息を吐けば吸えるように、すべては大いなる生命の営みの中にあります。自分をちっぽけな存在だと思わず、いつもその無限の可能性を信じていることができますように。
With love,
tOMoko ♥
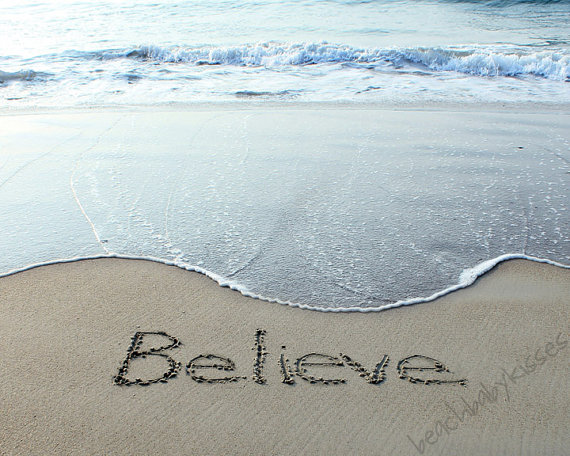
【ヨガコラム #4】スティラとスッカ
一昨年、昨年、今年と、3年続けてバリ島で誕生日を迎えることになりました。「縁は異なもの味なもの」と言いますが、それは人だけでなく、土地とのつながりもそうなのだと感じます。
伝統舞踊、音楽、絵画、彫刻などで知られるウブドは、バリの芸術と観光の中心地。ヨガが盛んで、大小のスタジオがあちこちにあり、世界各国からヨギたちが集まります。
誕生日の朝、緑に囲まれたウブドの滞在先で目覚め、テラスにつながる扉を解放して、いつものプラクティスをしました。慣れ親しんだ日常のシークエンス。それでも、吸う息、吐く息、そして、それぞれのヴィンヤサ(呼吸に合わせて身体を動かすこと)に、一つひとつ特別な味わいがあります。
それは、新しい歳になって初めてという新鮮さ。その後、テラスでいただいた朝食もそうでした。誕生日だけでなく、本当は毎日が特別な日。新しい呼吸で始まる新しい一日は、本来すべてが奇跡です。当たり前すぎて、なかなかそこに気づきを向けることは難しいですが、一日の中でほんの少しでも、そこに立ち返ることができるような歳にしたいと思います。
吸う息は受け取る呼吸。穏やかなウジャイ(胸式呼吸)で息を吸うと、前後、上下、左右に、ゆったりと胸郭が広がるのが分かります。その柔らかさは女性性の象徴です。吐く息は与える呼吸。ウジャイで息を吐くと、下腹部が内に入り、少し上に上がります。その強さは、男性性の象徴。相反するものの融合(ハタヨガ)は、そうやって呼吸の中にもともと存在しているものです。
『ヨガスートラ(歴史的なヨガの文献の一つ)』には、「アーサナ(ヨガのポーズ)は、安定していて、快適でなくてはならない」という有名な一項があります。サンスクリット語で、安定は「スティラ」。快適は「スッカ」。つまり、どのポーズにも、強さと柔らかさが同居すべきだということ。それは、無理やり作り出すものではなく、もともとわたしたちの呼吸(命)に備わっているもの。プラクティスの中で、そこに意識を戻すことで、すべては自然と最良のタイミングで花開いていきます。
それはマットの上でも、そしてマットの外でも同じこと。より自分が自分らしくあるために、強さも柔らかさも、愛おしむことができますように。そして、その調和への敬いと慈しみを、決して忘れることがありませんように。
With love,
tOMoko ♥
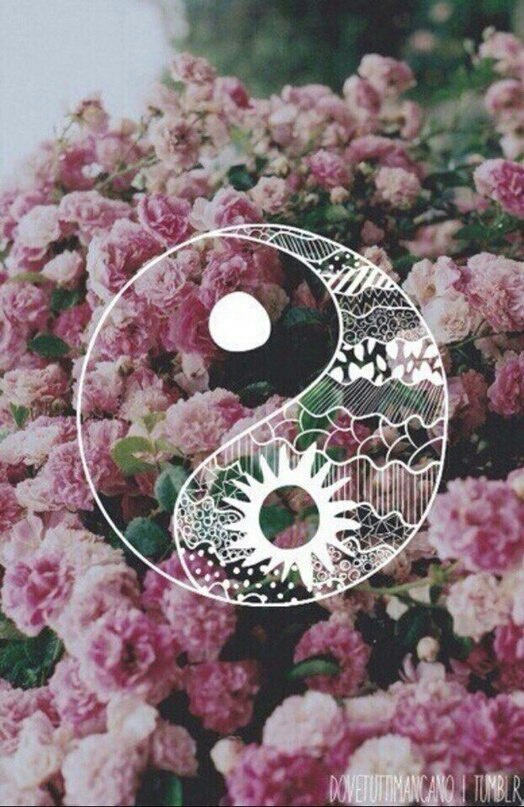
【ヨガコラム #3】Here and Now
5日ほど前から、パートナーの仕事の都合でバリ島のウルワツに来ています。縁あって、わたしにとっては6度目のバリですが、ここは初めてのエリア。慣れ親しんだウブドは山側で、こちらは海側。街の雰囲気も違い、色々なことが手探りでのスタートとなりました。
日本を離れての海外生活は、自由で華やかなイメージがあるかもしれませんが、実際はそれだけではありません。これまでの当たり前が当たり前ではない土地で、自分なりの心地良さを見つけていくには、もちろん個人差はあれ、ある程度の時間とエネルギーを要するものです。特にそのプロセスを経ている間、マインドはここではないどこかにさまよいがち。「あれがあったらいいのに」「これがあったらいいのに」ないものばかりに意識が向いて、あるものに気づくことが難しかったりもします。
マインドは、もともと「今」に留まっていることが苦手です。考えるということは、マインドの大切な仕事ですが、たいていその思考は、過去か未来に向いています。今を感じようと瞑想をしても、昨日起きた出来事が頭の中に浮かんできたり、明日は何をしようと思いが巡ってしまうのも、珍しいことではありません。
頭の中が騒がしいとき、心がなんだか落ち着かないとき。そんなときは、静かに自分の呼吸に気づきを向けてみるようにします。呼吸の速さ、深さ、質…。何一つ変える必要はありません。ただ自分の吸う息、吐く息を感じるだけです。呼吸を味わうために、まずは自ずと目を閉じたくなるもの。それだけで、意識は一つ内側に向いていきます。鼻呼吸が苦しくなければ、柔らかく唇を閉じ、鼻先を通り抜けていく吸気と呼気に意識を向けてみます。
外から空気が入って来る吸気の冷たさ、内から空気が出て行く呼気の温かさに集中してもいいし、呼吸に合わせて「吸っている」「吐いてる」と心の中で静かにくり返すこともできます。あるいは、吸う息で自分の内側に招き入れたいもの、吐く息で外側に送り出したいものを、心の声で唱えてみるのもいいかもしれません。例えば、吸う息で「愛(love)」、吐く息で「平和(peace)」など、恐らくそのときの自分に必要な言葉が自然と浮かんでくるはずです。
吸う息も、吐く息も、それぞれ今、この瞬間にしか存在しません。呼吸を感じるということは、今を感じるということ。過去でも、未来でもなく、今を生きている自分の存在に意識を向けるということです。呼吸があるということは、今ここに命があり、自分が生かされているということ。その喜びを味わうことで、目の前にある問題が即決するとは限りませんが、そもそも問題を「問題」とするものの見方や、自分の思考パターンに、何か突破口が見つかるかもしれません。
With love,
tOMoko ♡

【ヨガコラム #2】セルフメンテナンス
今日は久しぶりの休日。ふと思い立って、家にあるマグカップたちの茶渋を落としてみました。重曹と、水だけで汚れが落ちるスポンジで洗い上げて見た目もスッキリ。新品ではありませんが、ピカピカと輝いてカップたちも嬉しそうです。
よく考えてみれば、わたしたちのカラダも同じこと。定期的にメンテナンスをしてあげないと、こびりつかなくてもいいものがこびりつき、溜まらなくていいものが溜まってしまいます。カラダは機能して当たり前。その大前提のもと、マインド(頭)に指示されるまま、食べものや飲みものを詰め込んだり、たとえ声には出さなくても、自分のカラダに対して心ない言葉をかけてしまったり…。無自覚に虐げてしまっていることも、多いのかもしれません。
わたしたちも含め、世の中のすべてはエネルギーとして存在しています。そのエネルギーを健やかな状態に保つためには、与え、受け取ることのバランスが必要です。その代表例が「呼吸」。呼気、吸気と書くように、息を吐いて与え、吸って受け取ります。与えてばかりいれば、エネルギーは枯渇し、受け取ってばかりいれば膨満します。わたしたちの命が、もともと持っている呼吸のメカニズムはとても素晴らしく、人は息を吐いた分だけ、吸えるようにできています。つまり、呼吸を深めたいと思ったら、まずは深呼吸でたっぷりと息を吐けばいいのです。
ですが、これが食べものとなると、そう簡単にはいきません。呼吸の例を考えれば、排泄しただけ摂取すればいいのでしょうが、そこまで単純ではないのが厄介なところ。ヨガでは、カラダ、マインド、ハートということがよく言われますが、必ずしもその3つが、同じ声の大きさで、同じメッセージを発してくるとは限らないからです。
例えば昨日。プライベートと仕事で訪れていた京都滞在の最終日でした。朝起きたら、舌にわりと大きな口内炎ができていて、話すたびに歯にあたって痛みを感じます。外食が続いたのもあって、胃が疲れているのかも…とそのときは思いましたが、お昼を食べる頃には忘れてしまい、夕食は仕事を終えた安堵感、あるいはそのほっとした気持ちをより味わいたかったのか、がっつりお腹に溜まるものを食べてしまいました。
普段は丈夫な胃が、再び声を上げたのは、帰りの新幹線の中。痛みではありませんが、とても重たく、詰まった感じが、ベッドに入る前も、そして今朝起きてからも続きました。「ちゃんと声を聞いてあげられなくてごめんね…」カラダにお詫びをしながら、今日は極力胃を休ませるようにしています。おかげで少しずつ消化が進み、だんだんと軽さや空間も戻ってきました。茶渋を落としたマグカップと同じように、胃もほっとしているのが分かります。
わたしたちのカラダは、ゴミ箱ではありません。食べものも、感情も、むやみやたらに詰め込んでいたら、カラダは必ず悲鳴を上げてしまいます。この世に一つしかない大切な自分のカラダ。酷使させすぎて、参ってしまうことがないように、日頃のメンテナンスをぜひ心がけたいものです。
With love,
tOMoko ♡